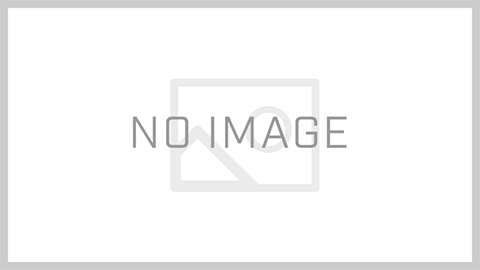薪ストーブは、暖房器具の中でも独特の魅力があり、自然の炎の暖かさを楽しめる点が人気です。しかし、どのような仕組みで暖まるのか、どの素材が適しているのか、燃焼効率を上げるための技術について知ることは、導入を検討する上でとても重要です。
本記事では、薪ストーブの基本的な仕組みや種類について、できるだけわかりやすく解説していきます。
薪ストーブが暖まる仕組み
薪ストーブは、電気を使わずに、薪を燃焼させて薪ストーブ燃焼室・煙突内に発生する上昇気流を利用して炎を起こす暖房機器です。
単純に薪を燃やすだけでなく、空気の流れや燃焼させる仕組みによって、部屋を暖めることができます。
まずは、薪ストーブが暖まる仕組みを「ストーブの構造」「吸排気の仕組み」「放熱ロス」の3つに分けて解説します。
1.ストーブの構造
薪ストーブは、基本的に「燃焼室」「煙突」「空気調整口」から構成されています。
燃焼室
薪を燃やすための部屋のことで、ストーブの中心的な部分です。
燃焼室で薪を燃やし、発生した熱がストーブ本体を暖め、部屋全体へ熱を伝えます。
燃焼室のサイズや形状はストーブによって異なりますが、効率よく燃やすために空気の流れがコントロールされる設計になっています。
煙突
煙突は、燃焼で発生した煙を外へ排出する役割を果たします。
また、適度な強さのドラフト(上昇気流)は、煙突から効率よく煙を外に吸い出し、室内で新しい空気を取り込みやすくするため、効率的で安定した燃焼に必要です。
煙突の断熱性能や高さ、曲がり方によって燃焼力や煙の流れが変わるため、煙突内の汚れや排気に大きく影響します。そのため、煙突を適切に設置することは非常に重要です。
空気取り入れ口
薪が燃えるためには酸素が必要です。
薪ストーブには「空気取り入れ口」があり、そこから新鮮な空気を取り込みます。
空気の量を調整することで、燃焼の強さや燃焼効率をコントロールすることができます。
2.吸排気の仕組み
薪ストーブの燃焼効率を高めるには、適切に空気を取り込み、煙を煙突から排出することが大切です。
薪ストーブが燃焼する際には「一次燃焼」と「二次燃焼」が起こります。
それぞれの場面で、どのように吸排気が行われるかを解説します。
一次燃焼のとき
空気の取り込み
一次燃焼用の空気取り入れ口は、燃焼室の下部に配置されていることが多いです。
外気導入口のある薪ストーブでは、外から空気を取り入れるためのダクトを設置します。
煙の排出
燃え始めのため燃焼温度は低く、可燃ガスなどが含まれているため白い煙が排出されます。

二次燃焼のとき
空気の取り込み
二次燃焼では、取り込んだ暖かい空気を一次燃焼の煙に吹き付けることで、再燃焼させます。二次燃焼用の空気は、背後から取り入れることが多いです。
煙の排出
一次燃焼で出る煙の中に残っている、不完全燃焼による成分(ススやタール)や可燃ガスを燃料にするため、より排気がキレイになります。
また、ガスを燃焼させるためオーロラのような幻想的な炎を楽しむことができます。

3.放熱ロス
薪ストーブで薪を燃やすと熱エネルギーが発生しますが、一部は「放熱ロス」として失われます。
放熱ロスの主な要因
放熱ロスの要因には次のようなものがあります。
1. 煙突からの排熱
燃焼によって生じた高温の排気ガスが煙突を通じて外部に排出される際、熱も一緒に逃げてしまいます。
適切な煙突の設計と断熱が重要です。
2. 未完全燃焼
薪が完全に燃焼しない場合、燃料中のエネルギーが十分に活用されず、熱として利用できない部分が生じます。
燃焼室内の空気量を増やしたり焚き付けの薪を入れたり、適切に燃焼できる環境に改善しましょう。
3. 薪の水分含有量
薪に含まれる水分が多いと、燃焼時にその水分を蒸発させるための熱が消費され、結果として利用可能な熱エネルギーが減少します。
十分に乾燥した薪の使用をオススメします。
薪ストーブの熱に関する用語
薪ストーブの性能を評価する際、以下の2つの指標をよく見かけます。
ここで用語の意味を確認してみましょう。
熱効率と放熱ロスの関係
熱効率が高いほど、放熱ロスは少なくなります。
例えば、薪ストーブの燃焼効率が80%(①)、熱効率が60%(②)の場合、薪の持つエネルギーの60%が室内暖房に利用され、20%(① – ②)が煙突からの排熱などで失われたことになります。

このように、燃焼効率と熱効率の差が放熱ロスを示しており、熱効率を向上させることで、放熱ロスを減らし、薪のエネルギーをより有効に活用することができます。
薪ストーブの仕組み まとめ
薪ストーブの暖まり方の違い
薪ストーブの基本的な仕組みは同様でも、次のような要因によって、体感的な暖まり方や燃焼効率が異なってきます。
放熱方式の違い

どう熱を伝えるか
素材の違い

どんな素材か
燃焼方法の違い

二次燃焼システムは何か
上記3つについて詳しく紹介していきます。
1. 放熱方式の違い
薪ストーブで生み出された熱は、さまざまな方法で部屋に伝わります。
代表的なものは「輻射式」と「対流式」の2つです。
それぞれ特徴があり、部屋の広さや使用する環境、求める暖かさによって適したタイプを選ぶことが重要です。
輻射式(ふくしゃしき)
輻射式は、燃焼室の熱をストーブ本体が蓄熱し、その熱を赤外線(輻射熱)として周囲に放射することで暖める方式です。
多くの薪ストーブに多く見られる方式で、特に鋳鉄製の薪ストーブはこの輻射熱を多く放出します。
輻射熱は、薪ストーブの全方向から放熱され、遠赤外線として直接物質に伝わり、人や室内の壁・床・天井などを暖めます。

● 日光のように、じんわりとした自然な暖かさが感じられる
● 空気を直接暖めるわけではないため、室内の空気が乾燥しにくく、ホコリも舞い上がりにくい
● 点火直後でも暖かさを感じられる即効性がある
● 熱が遠くまで届きにくく、離れた場所では暖かさを感じにくい
対流式(たいりゅうしき)
対流式は、薪ストーブで暖められた空気が上昇し冷たい空気が下降するという、空気の流れ(対流)を利用して部屋全体を暖める方式です。
最近の薪ストーブは、この対流式を取り入れているものが多いです。

● 空気を循環させ部屋全体を均等に暖めることができる
● 広い部屋や天井が高い空間を暖めたいときに適している
● 空気を循環させるため、室内の空気が乾燥しやすい
● 空気の流れでホコリが舞い上がることがあるため、アレルギーのある方は注意が必要
複合式(輻射式+対流式)
複合式は、輻射式と対流式の両方の特徴を組み合わせた方式です。
ストーブ本体からの輻射熱と、燃焼室と本体の間に空気層をつくり、暖めた空気の対流による暖房を同時に行います。

● 輻射熱で直接暖かさを感じつつ、対流で部屋全体を均一に暖めることができ、最も効率的
● 効率的に暖めるためには、薪ストーブの設置場所や部屋のレイアウトを工夫する必要がある
薪ストーブ放熱方式の違い:まとめ
薪ストーブの熱の伝わり方にはそれぞれ特徴があるので、部屋の広さや使用する環境、求める暖かさによって適したタイプを選びましょう。
● 輻射式
赤外線の輻射熱で物体や人を直接暖める方式
メリット: 自然な暖かさを感じやすく空気を汚しにくい
デメリット: 部屋全体を均一に暖めにくい
こんな場面に:小さな部屋やスポット暖房として使いたいとき
● 対流式
暖めた空気を循環させることで部屋全体を暖める方式
メリット: 広い空間でも均等に暖まりやすい
デメリット: 空気が乾燥しやすく、ホコリが舞い上がることがある
こんな場面に:広い部屋や複数の部屋を暖めたいとき
● 複合式
輻射式と対流式の両方を組み合せた方式
メリット: 部屋全体を効率よく暖めつつ、心地よい暖かさを提供できる
デメリット: 設置場所や設計によって効果が左右される
こんな場面に:心地よさと暖房効率のバランスがほしいとき
2.素材の違い
薪ストーブは、その素材によって性能やデザイン、暖まり方が異なります。主な素材として「鋼板製」「鋳鉄製」「その他の素材(耐熱セラミック・石材)」が挙げられます。
素材それぞれの特徴を紹介していきます。
鋼板製

素材の特徴
鋼板製の薪ストーブは、鉄板を切断・溶接して作られています。
鉄板が薄いため軽く、密閉度が高いのが特徴です。
熱伝導率が高く、焚き始めから短時間で室内を暖めることが可能です。
デザインの傾向
鋼板は加工しやすいため、モダンでシンプルなデザインが多く、大きなガラス窓を持つモデルもあります。
暖まり方の違い
熱伝導率が高いため、着火後すぐに部屋を暖めることができます。
ただし蓄熱性は低いため、火が消えると比較的早く冷めてしまいます。
● 立ち上がりが早く、すぐに部屋が暖まる
● 比較的軽量で設置しやすい
● デザインの自由度が高く、モダンなモデルが多い
● 輻射熱の持続時間が短い
● 鉄板の厚みが薄いと変形や劣化しやすい
鋳鉄製

素材の特徴
鋳鉄製の薪ストーブは、溶かした鉄を型に流し込んで作られています。
厚みがあり、蓄熱性に優れています。ただし、暖まるまでに時間がかかります。
デザインの傾向
クラシックで重厚感のあるデザインが多く、装飾性の高いモデルもあります。
伝統的な雰囲気を持ち、インテリアのアクセントになります。
暖まり方の違い
暖まるまでに時間がかかりますが、輻射熱を多く放出し、一度暖まると冷めにくく、長時間暖かさを維持します。熱の放出がゆっくりなため、安定した室温を保ちやすいです。
● 熱をため込む力が強く、暖かさが長持ちする
● 頑丈で耐久性が高い
● 重厚感のあるクラシックなデザインが魅力
● 立ち上がりが遅く、暖まるまで時間がかかる
● 重量があるため設置に工夫が必要
ハイブリッド(鋼板+鋳鉄)

素材の特徴
主に燃焼室などの炉内が鋼板、外装が鋳鉄の二重構造でつくられているタイプです。
高熱になる炉内を鋼板製にすることで熱収縮による鉄の疲労を軽減し、長く使用できるよう工夫されています。
暖まり方の違い
鋼板部分と鋳鉄部分の間に隙間をつくる構造にすることで対流熱を生み出し、輻射熱との相乗効果で効率的な暖房を実現します。
その他の素材

素材の特徴
耐熱セラミックや石材を使用した薪ストーブは、比熱が大きく、たくさんの熱を蓄えることができます。また、遠くまで輻射熱を届けることができるため、空間を均一に暖めることができます。
デザインの傾向
自然素材を活かしたデザインが多く、柔らかな雰囲気を持つものが特徴です。
石材やレンガなどを使用したものは、インテリアとしても魅力的です。
暖まり方の違い
暖まるまでには時間がかかりますが、一度暖まると長時間にわたって暖かさを維持します。薪が燃え尽きた後も、素材が蓄熱した熱で室温を暖かく保つことができます。
● 熱をため込む力が強く、暖かさが長持ちする
● 頑丈で耐久性が高い
● 自然素材ならではの表情あるデザイン
● 本体が蓄熱するまで時間がかかるため、即暖性は低い
● 重量があるため設置場所の検討が必要
薪ストーブ素材の違い:まとめ
薪ストーブの素材選びは、使用目的やライフスタイル、デザインの好みによって異なります。自分に合った素材を選び、快適で効率的な薪ストーブ生活を楽しみましょう。
● 鋼板製
薄い鉄板を加工して作られる。
メリット: 立ち上がりが早くすぐに暖まる・軽量で設置しやすい
デメリット: 蓄熱性が低く、火が消えるとすぐに冷める
デザイン:モダンでシンプルなデザインが多い
こんな場面に:短時間で素早く暖めたい場合に最適
● 鋳鉄製
溶かした鉄を型に流し込んで成形する
メリット: 蓄熱性が高く、長時間暖かさを維持できる・耐久性が高い
デメリット: 立ち上がりが遅く、暖まるまでに時間がかかる・重くて設置が大変
デザイン:クラシックで重厚感のあるデザインが多い
こんな場面に:暖かさを長時間維持したい方におすすめ
● その他の素材(耐熱セラミック・石材)
耐熱セラミックや石材でできるている
メリット: 高い蓄熱性で長時間の暖かさを維持できる
デメリット: 暖まるまでに時間がかかる・高価で設置が難しい場合がある
デザイン:自然素材を活かしたデザインやインテリア性の高いモデルが多い
こんな場面に:暖かさを長持ちさせたい人やデザインにこだわる人向け
3.燃焼方式の違い
薪ストーブの燃焼効率を高めるために、二次燃焼技術は欠かせません。
二次燃焼とは、薪が燃えたときに発生する煙(未燃焼ガス)が550℃以上でもう一度燃えるという性質を最大限に利用する仕組みです。
熱を再利用する二次燃焼には、さまざまなメリットがあります。
● 排気がよりクリーンになる
● 燃焼時間が長くなる
● 薪の消費量を抑える
二次燃焼の燃焼方式には主に「クリーンバーン方式」「触媒方式」「ハイブリッド方式(クリーンバーン+触媒)」の3種類があります。
それぞれの仕組みや特徴、メリット・デメリットについて解説します。
クリーンバーン方式

仕組み
クリーンバーン方式は、燃焼室内で一次燃焼と二次燃焼を行う非触媒方式の一つです。
一次燃焼で薪から発生した可燃性ガスや微粒子に対し、高温の二次燃焼用空気を供給することで再燃焼させ、煙や煤を燃やし尽くします。これにより、排気をクリーンに保ちます。
特徴
ストーブの構造がシンプルで、操作やメンテナンスが容易です。
燃焼室内で一次燃焼・二次燃焼を行うため、炎のゆらめきを楽しむことができます。
● 操作が簡単で、燃焼が安定している
● 構造がシンプルなため、掃除や部品交換などメンテナンスが容易
(触媒方式と比較すると)
● 排気ガスのクリーンさは劣る
● 燃焼効率が若干低い場合がある
触媒方式

仕組み
触媒方式は、燃焼室内に触媒を設置し、薪から発生する煙が触媒を通過する時に化学反応を起こし、煙や煤を高温化させ燃焼させる方式です。
薪ストーブの触媒は、パラジウムやロジウムなどの貴金属が塗布されたセラミック製で、目の細かい蜂の巣状になっています。
高温になりやすいセラミックの特性に加え、表面に塗布された貴金属の化学反応により、煙を急速に高温化し二次燃焼を促します。
特徴
触媒自体が260℃を超えると二次燃焼を開始するため、クリーンバーン方式より早く二次燃焼が始まり、効率よい燃焼とクリーンな排気を実現します。
● 薪の消費量を抑えつつ、高い暖房効果を得られる
● 排気がクリーンで、環境負荷が低減される
● 空気の調整や触媒の管理が必要で、操作がやや複雑
● 触媒の定期的な点検や交換が必要で、維持管理に手間がかかる
ハイブリッド方式(クリーンバーン+触媒)

仕組み
ハイブリッド方式は、クリーンバーン方式と触媒方式を組み合わせた燃焼方式です。
まずクリーンバーンで一次燃焼と二次燃焼を行い、その後、触媒を通じてさらに未燃焼ガスを燃焼(三次燃焼)させます。これにより、高い燃焼効率とクリーンな排気を両立します。
特徴
両方式の利点を組み合わせることで、効率的で環境に優しい燃焼を実現します。
● 薪の消費を抑えつつ、高い暖房効果とクリーンな排気を実現
● 触媒方式に比べて、操作が比較的簡単
● 複雑な構造のため、初期投資やメンテナンスコストが高くなる傾向がある
● 触媒部分の定期的な点検や交換が必要
薪ストーブの燃焼方式 まとめ
求める機能や使用目的に合わせて、最適な燃焼方式を選びましょう。
薪ストーブをより効率的に使うためには、燃焼方式の違いを理解することが重要です。
● クリーンバーン方式
二次燃焼用の空気を取り込み、煙や未燃焼ガスを高温で再燃焼させる方式
メリット: 構造がシンプルで操作とメンテナンスが簡単・美しい炎が楽しめる
デメリット: 燃焼効率や排気のクリーンさは触媒方式に劣る
こんな場面に:簡単な操作で使いたい方におすすめ
● 触媒方式
触媒を通して未燃焼ガスを低温で再燃焼させ、効率を高める方式
メリット: 高い燃焼効率を実現し、薪の消費量を抑えられる・排気が非常にクリーン
デメリット: 操作がやや複雑で、触媒の定期的なメンテナンスが必要
こんな場面に:燃焼効率を重視し、環境に配慮したい方に最適
● クリーンバーン方式
クリーンバーンと触媒の両方を組み合わせ、効率的に燃焼する方式
メリット: 燃費が良く、クリーンな排気を実現・操作も比較的簡単
デメリット: 構造が複雑で、初期費用やメンテナンスコストが高め
こんな場面に:燃費とクリーンさを両立させたい方に向いている
薪ストーブの仕組みと種類 まとめ
薪ストーブは、暖房方式や素材、燃焼技術によって特徴が大きく異なります。
導入を検討する際は、自分のライフスタイルに合ったタイプを選ぶことが重要です。
• 即暖性なら… 鋼板製がオススメ
• 暖かさを長く持続させたいなら… 鋳鉄製・石材製がオススメ
• 燃焼効率を重視するなら… 燃焼方式をチェック
• 環境に優しい暖房を求めるなら… 触媒方式がオススメ
薪ストーブを上手に活用すれば、薪の消費を抑えつつ快適な暖房を実現できます。
ご自身のライフスタイルに合った薪ストーブを選んで、心地よい暖かさを楽しんでください。
薪ストーブ 製品情報